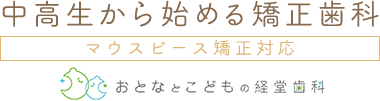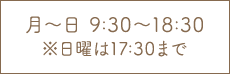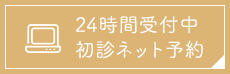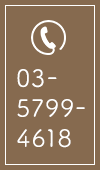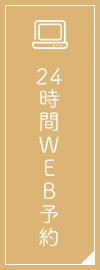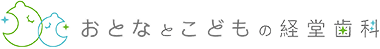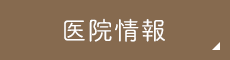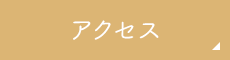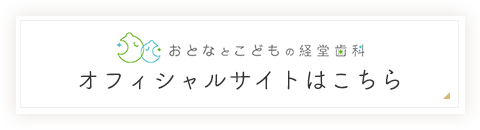悪い歯並びと原因
叢生(そうせい)、八重歯、乱杭歯
叢生とは、ガタガタ・デコボコの歯並びのことで、乱杭歯とも呼ばれます。犬歯が飛び出している「八重歯」、歯がねじれている「捻転」も叢生に分類されます。症状がひどいと、歯が埋もれてしまう「埋伏歯」になる場合があります。
叢生の原因はさまざまですが、代表的なのは顎の骨が小さくて歯が顎のスペースに収まりきらないことです。歯磨きが難しくなるので、磨き残しによるむし歯や歯周病のリスクが高まります。
上顎前突、出っ歯
上顎前突は出っ歯や下顎遠心咬合と呼ばれます。下の歯よりも上の歯が6mm以上突出している場合に診断されます。前歯が外側に向いて生えていたり、口を閉じている感覚なのに閉じられていなかったりと、見た目に影響を及ぼします。原因は骨格的な問題のほか、指しゃぶりや口呼吸、上下の顎のアンバランスな成長などです。
空隙歯列、すきっ歯
空隙歯列とは、歯と歯のすき間が大きく開いた「すきっ歯」のことです。上の前歯のすき間が大きい場合、サ行を発音しづらくなるほか、笑ったときに口元が気になります。空隙歯列の原因は、顎に対して歯が小さい、歯の本数が少ない、前歯を舌で押す行為などです。
開咬
開咬とは、口を閉じたときに奥歯は噛み合っているのに上下の前歯の間に空間ができる状態です。前歯で食べ物を噛み切れないため、奥歯に負担がかかります。また、上下の前歯の空間から空気が漏れて、発音しづらくなります。
さらに、奥歯に集中して力がかかるため、奥歯に大きな負担がかかるというリスクもあります。原因は、遺伝的に骨格が面長であることのほか、歯を舌で押す、口呼吸、指しゃぶりなどです。
過蓋咬合(かがいこうごう)
過蓋咬合は、下の歯に上の歯が大きく被さった状態です。下顎を動かしづらくなったり顎の骨に大きな負担がかかったりします。その結果、顎関節症を引き起こし、開口障害や肩こり、頭痛などに繋がる場合もあります。
ひどいケースでは、下の前歯が上の前歯の歯茎に食い込み、口内炎や細菌感染が起こる場合もあります。原因は、顎の骨の成長状態が不十分であったり、むし歯で失った奥歯を放置したりすることです。
反対咬合、下顎前突、受け口
反対咬合は、前歯が3本以上噛み合わせが反対になっている状態です。本来、上の前歯が前に出るところ、下の前歯の方が前に出ています。前歯が傾いているケースと骨が全体的に前に出ているケースがあります。
原因は、遺伝的に上下の顎の骨がアンバランスであることや、舌の位置が通常よりも低いことなどです。特徴的な顔立ちになるため、強いコンプレックスを持つ方が少なくありません。また、発音が悪い、食事をとりにくいなどの問題も起こります。上顎が成長する小学校2~3年生頃までに治療を始めることが大切です。
上下顎前突
上顎前突症は、上下の歯あるいは顎の骨が前方へ突出している状態です。横から見ると、顔の下半分だけが前に出ています。上下の前歯が外側に向いているために、口元を突き出しているように見えることも特徴です。口を閉じにくくなるため、口呼吸になりがちです。さらに、口を無理に閉じようとすると顎に梅干しジワができます。
原因は、唇や舌の筋肉や骨格などのバランスが悪いことです。
交叉咬合
交叉咬合は、下の奥歯よりも上の奥歯が外側に位置した状態です。原因は、骨格の歪みや変形、上下の顎・歯列のアンバランスなどです。頬杖や片側噛み、口呼吸、舌の位置が通常よりも低いといった要因で交叉咬合になります。放置すると、成長と共に顎が歪み、顔が左右非対称になる恐れがあるため、子供の頃から治療を始めることが大切です。
切端咬合
切端咬合は、噛んだときに上下の前歯の先端がぶつかる状態です。前歯に大きな負担がかかり、割れたり欠けたりする恐れがあります。原因は、前歯を舌で押す癖、口呼吸、顎の骨の成長がアンバランスであることです。子供の頃になりやすく、そのまま放置すると永久歯に生え変わってから反対咬合になるケースもあります。
先天性欠如
先天性欠如とは、先天的に永久歯が欠如している除隊です。原因は不明ですが、遺伝的要因や妊娠中の栄養状態、薬物の副作用などが関連しているとの説があります。中でも前から2番目の側切歯、5番目の第二小臼歯に起こりやすい症状です。歯が永久歯に生え変わる時期を大きく過ぎているのに生え変わらない場合は、先天性欠如の可能性があります。
乳歯は永久歯と比べてむし歯になりやすく、むし歯が神経に到達するまでのスピードが速いので、30代前後で失うケースがほとんどです。
過剰歯
過剰歯は、本来よりも歯の本数が多い状態です。上顎の前歯にみられることが多く、歯の大きなねじれ、すきっ歯などの原因になる場合があります。また、過剰歯の中でも歯の頭の向きが反対になっているケースでは、放置すると鼻の中に歯が出てくることもあります。原因は不明ですが、外傷の影響や遺伝的要因で、歯の元になる歯胚が多く作られたり分裂したりすることといわれています。
過剰歯によって歯並びが悪くなっていたり、歯根を溶かすリスクがある場合は抜歯します。
萌出遅延や埋伏
萌出遅延や埋伏は、永久歯があるのに平均的な生え変わりの時期を過ぎても生えてこない状態です。一般的に、周りの子供よりも3年以上永久歯が生えてこない場合に疑われます。
反対側の歯が生え変わっている場合は、半年以上経過しても生えてこない場合に萌出遅延や埋伏を疑ってもよいでしょう。原因は、永久歯が生えるスペースが不足している、歯茎が厚い、歯の位置や向きの問題などです。
必要に応じて外科的な処置で永久歯を生やしますが、周りの歯に影響を及ぼす場合は抜歯を検討します。
歯並びが悪いとどうなる?
歯並びが悪い状況を放置すると、食べ物が歯と歯の間に詰まりやすかったり歯ブラシがすみずみまで届かなかったりするため、むし歯や歯周病のリスクが高まります。また、特定の歯に大きな負担がかかることで歯並びがさらに乱れたり、顎関節症になったりする場合もあります。
顎関節症になると、頭痛や肩こりなど全身の症状を引き起こす場合もあるなど、歯並びの問題は全身の健康にも深く関係しているのです。歯並びの種類に応じて適切な治療を受けて、きれいな歯並びへ整えることが大切です。
きれいな歯並びは、すみずみまで歯ブラシが届くうえに食べ物が詰まりにくく、全ての歯に力が均等にかかります。健康寿命も延び、より長く快適な日々を過ごせるようになるでしょう。歯並びのお悩みはできるだけ早く対処することが重要ですので、どうぞお早めにご相談ください。